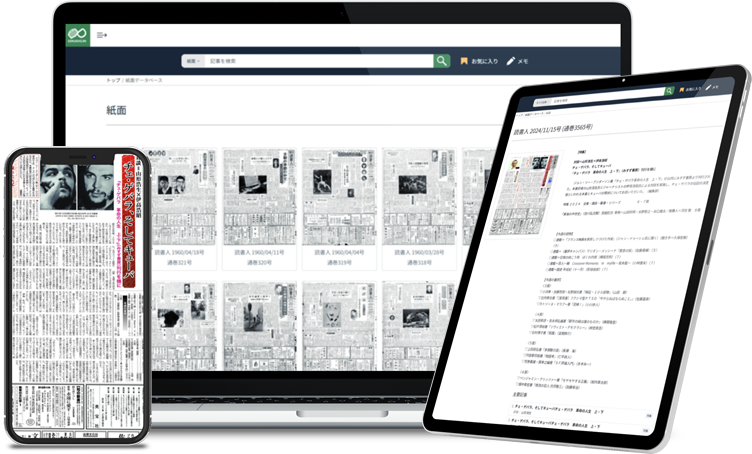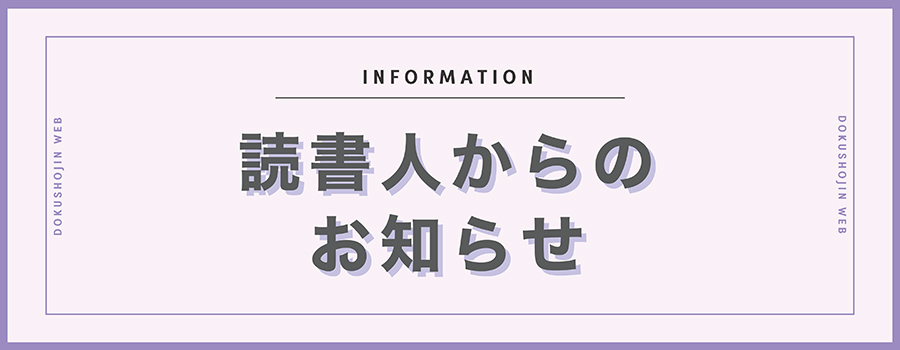週刊読書人WEBとは? About Dokushojin WEB
『週刊読書人WEB』は、1958年以降の本の批評記事(=書評)を収録したオンラインデータベースです。
『週刊読書人』(毎週金曜日発売)は1958年に創刊した伝統ある<書評新聞>。
質の高い書評はもちろん、文学界のニュース、作家、美術家、映画監督たちのインタビューも多数掲載。

『週刊読書人WEB』が
確かな情報を提供できる理由
日本一の書評掲載点数
 年間約700点の書評を掲載、他の媒体を圧倒する情報量
年間約700点の書評を掲載、他の媒体を圧倒する情報量 書評・記事・広告等すべてを合わせると、年間約2万冊の書籍を取り上げている
書評・記事・広告等すべてを合わせると、年間約2万冊の書籍を取り上げている
質が高く信頼のおける書評記事
 大学教授、専門家、批評家が執筆した署名記事を掲載
大学教授、専門家、批評家が執筆した署名記事を掲載 国内外の年間600名以上の執筆者が寄稿。常に新たな執筆者の発掘に努めている
国内外の年間600名以上の執筆者が寄稿。常に新たな執筆者の発掘に努めている 偉人、文豪たちの過去の書評記事も収録
偉人、文豪たちの過去の書評記事も収録 学者や研究者だけではなく、全国の図書館や書店員からも高い評価を得ている
学者や研究者だけではなく、全国の図書館や書店員からも高い評価を得ている
優れた本の選定
 書評対象となる本は、選書のプロである読書人編集部が1点ずつ編集会議を経て選定
書評対象となる本は、選書のプロである読書人編集部が1点ずつ編集会議を経て選定 一般雑誌では取り上げられないような専門書、優れた本にスポットライトを当て、積極的に紹介
一般雑誌では取り上げられないような専門書、優れた本にスポットライトを当て、積極的に紹介
『週刊読書人WEB』の機能

-
 1958年以降の『週刊読書人』すべてが検索・閲覧可能
1958年以降の『週刊読書人』すべてが検索・閲覧可能1958年以降、1年間に約50冊発行してきた『週刊読書人』。そのすべて(約3300号)が検索して閲覧できるようになりました。
また、有料会員のお客様は、毎週金曜日に発売される最新号もお読みいただけます。
年代、書籍名、評者名、作家名、、、気になるキーワードで検索。文壇の歴史を思う存分冒険しましょう!
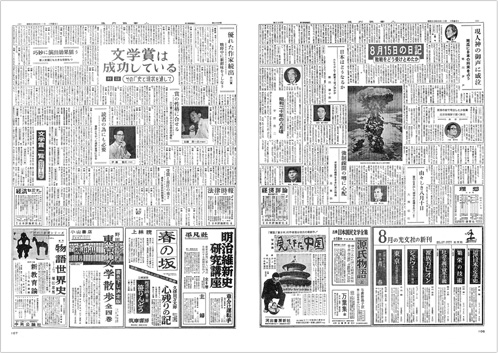
-
 マイページ機能でお気に入り記事をブックマーク
マイページ機能でお気に入り記事をブックマーク『週刊読書人WEB』は、操作性の高い新聞ビューワーに加え、「マイページ機能」も搭載。
お気に入り記事のブックマークや、気になる文章のマークアップなど、自分だけのオリジナルメモスペースを作ることができます。お気に入りの連載記事をブックマークすれば、カスタマイズされた自分だけの『MY読書人』が完成。
じっくり読みたかった記事を、いつでも、どこでも、好きな時間に読み返すことができます。

-
 ダウンロード・切り抜き印刷に対応
ダウンロード・切り抜き印刷に対応お客様からご要望があった紙面データのダウンロード、印刷に対応。※ご使用は規約の範囲に限ります。
画面上だけではなく、紙で読みたい人にもおすすめです。さらに「切り抜き印刷・ダウンロード」機能も搭載し、スクラップブックの作成も簡単に。

-
 ここでしか見られない『週刊読書人WEB』限定コンテンツ
ここでしか見られない『週刊読書人WEB』限定コンテンツ『週刊読書人』の紙面には掲載しきれないインタビューや対談も、『週刊読書人WEB』に完全版を収録。
また、『読書人』で開催されたイベントやセミナーのアーカイブ動画も見放題。予定が合わない、遠方で参加できないという方にも、本の街・神保町の空気をお届けします。
ほかでは見ることのできない、知ることのできない本の裏話、新しい発見が満載です!

\ 18,000円 /年 (税込)で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます/
今すぐ『週刊読書人WEB』に入会する機能と料金 Price
歴史的価値のある資料を、より多くの皆様にご利用いただきたく、データベース機能が追加されても、これまでと変わらない料金で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます。
| 機 能 | 詳 細 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 |
|---|---|---|---|---|
| 無 料 | 無 料 | 18,000円/ 年(税込) | ||
| メルマガ受信 | 毎週金曜日配信 | × | ● | ● |
| データベース検索 | 検索結果は表示されますが記事詳細は読めません | × | ● | ● |
| 定期購読(創刊号~最新号まで) | 契約日から1年間、創刊号から最新号まで購読可能 | × | × | ● |
| データダウンロード・印刷 | 切り抜き機能付きご使用は規約の範囲に限ります | × | × | ● |
| お気に入り記事ブックマーク | × | × | ● | |
| テキストのハイライト | テキスト情報が登録されている記事に限ります | × | × | ● |
| アーカイブ動画視聴 | 契約日以降に開催されたアーカイブ動画がすべて見放題 | × | × | ● |
*定期購読開始後の途中解約はできませんので
ご注意ください。
\ 18,000円 /年 (税込)で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます/
今すぐ『週刊読書人WEB』に入会する無料会員登録で『週刊読書人WEB』を体験することができます。データベース検索を是非お試しください。
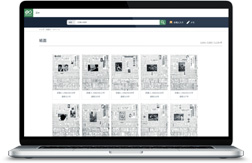
「週刊読書人」に関するご相談・お問い合せは専門フォームにてご連絡ください。